独学ギターといえば教則本。
実際に「買ってよかった」と感じた本を紹介します。
※追記
わたくし、ここ数年でDTM遊びを覚えました。
いま、脳が震えるダンスミュージックを作曲しています(真顔)
執筆当時は無かった無料で学べる最強音楽理論サイトを見つけたので、そちらも紹介します。
Youtubeコンテンツも充実してきたので、演奏フォームは教え方が上手なギタリストの動画で見て学ぶのが近道。教則本は「楽譜が載っている基礎練もの」を何冊か手元に置いて、飽きないよう味変して使うのがいいかなと思います。いま、私がギターを始めるならそうします。
以上追記でした。
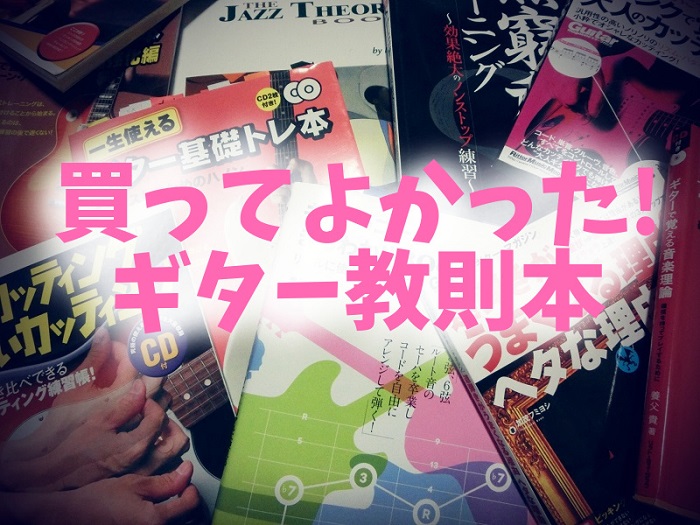
ギター初心者の方は「ギター入門書」から始めるのもアリです。
それではいきましょう!
【ギターの基礎系】
一生使えるギター教則本
渡辺具義『一生使えるギター基礎トレ本 ギタリストのためのハノン』
この本を最初に紹介した理由は「これ1冊で大体のことがわかる」から。
「ハノン」の名にふさわしいボリューム。
はじめに「ギター指板を5分割する」考え方を学びます。
次は左手の運指練習。指のバタつきを抑えるトレーニングです。指に「人(1)、中(2)、薬(3)、小(4)」と数字を割り当てて弾きます。
そのあと、ストレッチを兼ねた指の独立練習やハンマーオン/プルオフ練習など、徐々にステップアップしていきます。
右手のピッキングは、ギター初心者でも行える簡単なフレーズからはじめます。アルペジオ、ストローク、各種音符(休符)のピッキング、単音/コードカッティングなど。
両手の基本的なエクササイズのあとは、本格的なトレーニング。
「CAGED」ポジション別に、スケール、コードなどを徹底的に練習します。
※「Aポジションのメジャースケール・3度シーケンス」でまるまる1ページ使うペース。
繰り返し練習することで、弾きたい音を瞬時に見つけられるようになるでしょう。
「ギター基礎トレ本」の名に相応しい一冊。体と頭を使ってギター指板を理解する。おすすめの教則本です。同じ著者の本を5冊ほど買いましたが、1冊目には本書がオススメ。
+α
「ギターの基礎系」その他教則本。
・いちむらまさき『100個のフレーズを弾くだけで飛躍的にギターが上達する本』
「偏ったジャンルだけ弾いている」「基本的な奏法をフレーズ付きで知りたい」「ギターのフレーズって、何がどうなってんのかよくわからない」という方にとって、参考になる1冊。
ギター初心者の方もそうですが「そろそろオリジナル・フレーズ(アレンジ)を作りたい」という中級者の方にもおすすめ。
100個のフレーズの中に、ギターにおける基本的な奏法、主要ジャンルで耳にするフレーズ、応用の利きそうなフレーズが入っているので「ギターという楽器でできる奏法を一通り知る」目的で読んでみるのもあり。
ただ、読者レビューにある「フレーズがカッコ悪い」というのは本当です(失礼)。ですが、この本の魅力はそこではないと思います。練習用としては十分です。
【音楽理論系】
SoundQuest
冒頭で紹介していた最強の音楽理論サイトがこちらです。
難しい内容も、理解しやすいように書かれています。
独自の理論が少しありますが、基本は音楽理論系の洋書を元にした内容だと思います。手持ちの輸入本と同じ内容も載っていました。
音楽理論は使わないと忘れます。
でも、DAWで編曲中に本を引っ張り出すのはダルいです。
そんなとき、私はこのサイトをポチッとしています!
ただ、ギター独自の奏法は書かれていません。
ギターはパワーコードをはじめ、指板に基づいた(ハーモニーよりも奏者の弾きやすさを優先した)奏法が多いです。
これに関しては、好きなギタリストの曲を1曲まるまるコピーするのがおすすめ。
なんやかんや手癖や弾き慣れたポジションで弾いている人が多いので、カッティングとかは耳コピ(動画で目コピ)が効率的。わたしも、ニコ動ギタリストのカッティングをめちゃコピーしていました。
とくに妹姫(シスプリ)さんのカッティングフレーズが、シンプルでかっこよくて好きでした。『イージーデンス』とか何回も再生したな……なつかし
Youtubeの弾いてみた界隈には、女装文化あるんですかね。
初めて学ぶ音楽理論
宮脇俊郎『最後まで読み通せる音楽理論の本』
めちゃめちゃ簡単。入門者にはうれしい1冊。
正直、私にとってこの本は「はじめの1冊」ではないので、(既に知っている内容だったので)最後まで読んでないです。”おそらく”最後までわかりやすい。
宮脇俊郎さんの本なので、間違いないはず。
この1冊で音楽理論の基礎はバッチリ
井原恒平『作曲基礎理論~専門学校のカリキュラムに基づいて~』
膨大な内容。
著者は専門学校の元講師。
専門学校のカリキュラムを参考に書かれた、作曲の基礎理論書とのこと。
ページ数「500超」とありますが、ボリュームより何よりまず「目次」をご覧ください。少し理論を学ばれた方なら、さっと目を通しただけで欲しくなります。私は目次を見て即買いしました。
少なくとも3回は読みましたが、読むたびに理解が深まります。
まず「Chapter1:仕事としてのDTM関連のソフト&ハード」は、飛ばしてください。「Chapter2:音程」から理論です。内容は『新・実践コードワーク』を土台に、マーク・レヴィンのジャズ理論とクラシック系理論の”基礎”をまとめたイメージ。
説明は丁寧ですが、簡単ではありません。
音楽理論は「理論」と言っていますが、完璧ではありません。「フレーズによっては、この音も使える」ことが普通で、学ぶほどに「基本となる考え方」の大切さを思い知ります。
1項目に多くの説明を割けない(ページ数・内容の限られた)理論書だと、「このスケールでは、この音がアヴォイド・ノートです」とだけ書いて理由の説明は無し、ということも珍しくありません。
「究極的には全ての音が使える」音楽の世界で、「理論の元となる考え方」まで教えてくれる本は貴重。紹介文の一行「専門学校のカリキュラムを参考に」は伊達じゃない。
さらっと読める量じゃないので、本気の方におすすめです!
あと、めちゃくちゃコスパがいいです。
※「DLsite」はPDFなので、「Amazon」のKindleよりデータが扱いやすいです。
ジャズ理論の定番
Mark Levine(著)/愛川篤人(訳)『ザ・ジャズ・セオリー』
ジャズ理論を深めるなら、この1冊。
というより、日本語(翻訳含む)でジャズ理論書となると選択肢は限られます。中でもマーク・レヴィンは有名。
理論と実践のつながりが、具体的にみえる本書。
とにかく例が多く、例えば「マイナー・メジャー・コード」だけでも
・Gigi Gryce『Minority』の4小節
・Horace Silver『Nica’s Dream』の3小節
・Billy Strayhorn『Chelsea Bridge』の3小節
・Wayne Shorter『Dance Cadaverous』の4小節
・George Gershwin『Summertime』の3小節
が紹介されています。
英語版は半額なので、読める方はそちらを。
中身については「『ザ・ジャズ・セオリー』について」にて↓
+α
「音楽理論系」の、その他教則本を紹介します。
・菊地成孔/大谷能生『憂鬱と官能を教えた学校 上』 / 『憂鬱と官能を教えた学校 下』
読み物として面白い。現在のポピュラー音楽で広く使用されている「バークリー・メソッド」を、広い知識とユーモアを交えて掘り下げた1冊。簡単に理論を学んだ後で読むと、より楽しめます。
Amazonで人気だったので、一通り読んでみました。個人的に「サブドミナントの定義」と「テンションの簡単な考え方」がおすすめポイントです。ただ、説明が端的で、具体例は比較的薄く(ややジャズに偏り)、教科書のような印象です。”どれか1冊”であれば、「質」「量」「わかりやすさ」どれにおいても、井原恒平『作曲基礎理論~専門学校のカリキュラムに基づいて~』をおすすめします。
【コード・ブック系】
「形」で覚えるコードから、一歩先に
渡辺具義『ギター・コードまるわかりBOOK リアルに使えるコードワーク編』
はじめに紹介した渡辺具義さんの著書。
オープン・コードの押さえ方、テンションなど、使える音を指板図にまとめて紹介し、実際にフレーズを弾いて身につけるという実践的な本。オープン・コードを学べば「CAGEDシステム」で応用することは容易なので、コードを覚える基礎本としてもおすすめです。
「6・5弦ルートのコード以外は自身が無い人」「指板上の音の理解が曖昧な人」「コードの省略型、インターバルの位置関係をきちんと理解したい人」におすすめ。コードを「押さえる形」で把握する段階から、一歩進みたい方に。
ギター初心者のコード理解
・渡辺具義『ギターコードまるわかりBOOK−フォームと進行の両面から迫る!』
同じく渡辺具義さんの本。
ギター初心者には取っ付きやすい分、『ギター・コードまるわかりBOOK リアルに使えるコードワーク編』より内容が薄いです。”簡単”なコード・ブックを求める方は、こちらも選択肢に。
+α
「コードブック系」の、その他良書を紹介します。
こちらも、Amazon等で数ページほど中身を確認できますので、購入前に必要かどうか検討してください。
ギターを始めたばかりの方が覚えるであろうコードは、この本の”2割程度”です。2割の根拠は、私がパッと開いたページで、よく使う押さえ方が(10個中)2個だった為。『オープン・コード事典』(※辞典ではない)のタイトル通り、コードの押さえ方が900個も載っています。
ある意味、これさえあれば他のコード表は必要ないでしょう。ただ、「コードの作り方がわからない」という方は、先に別の本で基礎を固めてください。「いつか使うかも」「コードの辞書として置いておきたい」と考えれば、あって損はない1冊。
【フォーム系】
ギターのプレイ・フォームを考える
宮脇俊郎『ギターマガジン グングンうまくなる究極のプレイフォーム』の新版↓
ギターにも、弾きやすいフォームがあります。また、良い(安定した)音を出しやすいフォームがあります。
ギターのプレイスタイルは人それぞれで良いと思いますが、変なフォームのせいで速弾きが弾きにくかったり、カッティングがやりにくかったりと・・損をするのは避けたい。
打楽器だと、ある程度正しいフォームで演奏しなければ、成長はおろかケガにつながります。「脱力」や「大きな筋肉」を使う方法、スピードに合わせて「ヒジ→腕→手首→指」のように体の動かす箇所を変えたりなど、基本的な奏法の習得は必須。
しかし、ギターは非効率的なフォームでも「とりあえず弾ける」ので、フォームは軽視されがち。この本は、ギターで必要なほとんどのプレイ・フォームがまとめられています。私も「もっと前に読んでおけば良かった」と感じた1冊。
【テクニック系】
カッティングのフレーズ作り
山口和也 『16ビートが身につく! ファンクで覚える大人のカッティング』
バッキングの基礎、カッティング。「でも、何を弾いたらいいかわからない」「基本的なカッティング・フレーズを知りたい」方にオススメの1冊。「コード・カッティング」「単音カッティング」「ノリの出し方」「リズム・パターン」「カッティングで使えるテクニック」を知りたい方は是非。
フレーズを演奏することで、肉体的にもカッティングを記憶できます。オリジナル・フレーズにおいて”手グセ”は悪く言われがちですが、少なくともカッティングにおいては重要です。どんどん”カッティングっぽい”フレーズを蓄えましょう。
カッティングの基礎
宮脇俊郎『良いカッティング 悪いカッティング』
カッティング全般に当てはまる”基礎”に焦点を当てた本。
カッティングのフォーム、良い音の出し方、フレーズの作り方、実際の演奏と、バランス良くまとめられています。「音にキレが無い」「ミュートが上手くできない」と悩んでいる方、「ピックの持ち方」「右手の振り方」など基本のフォームから学びたい方にもおすすめ。
速弾きのレベルアップ
加茂フミヨシ『速弾きがうまくなる理由 ヘタな理由』
加茂フミヨシさんが教える”速弾き”。
もう間違いない1冊でしょう。
ただし、「速弾き練習、今日からはじめます」という方にとっては「テンポの合格ラインが高い!」と感じられるかもしれません。その場合、各々で目標テンポを下げて「とりあえず1周」してください。「合格テンポをクリアするまで次に進まない!」という自分ルール設定は、(おそらく)効率的なレベルアップに繋がりません。
個人的には「1年くらい自己流で速弾き練習してきたけど、停滞気味」という方に、最も効果的な本だと思います。「短い(1小節以内の)フレーズなら弾ける」「スケールをなぞるだけなら速い」といった方にもおすすめ。
右手・左手それぞれに的を絞った練習。説得力のあるポイント解説と、効果的な練習フレーズ。何より「既存曲のコピーだけでは、滅多に出会わないフレーズ」を練習できます。テクニカルなギタリストでも無い限り、あえて”弾きにくいフレーズ”を入れることは稀。ポップスの速弾きコピーだけでは習得できないテクニックも身に付く、レベルアップに最適の教則本。
順序立てて、練習メニューが組まれています。速弾きの定番と言えば『地獄の〇〇』シリーズですが、あちらは機械的(メカニカル)なフレーズ練習向け。
+α
「速弾き」の、その他教則本を紹介します。
・小林 信一『地獄のメカニカル・トレーニング・フレーズ平成を生きるメンズのアニソン編(CD付) 』
速弾きフレーズ本の定番『地獄の〇〇』シリーズ。コツ・ポイント・フォームについては、加茂フミヨシさんの『速弾きがうまくなる理由 ヘタな理由』がおすすめ。
ちなみに私は、地獄シリーズは第1弾と第2弾までしか持っていません。
サイト的に「アニソン編」を載せましたが、検索したところ「入隊編」や「ゲーム・ミュージック編」「クラシック名曲編」など気になる作品が出ていました。「弾いてみたい!」と思った1冊から、手にとってみてください。
【フレーズ系】
コード・トーンをフレーズに
道下和彦『ギター無窮動(むきゅうどう)トレーニング 効果絶大のノンストップ練習』
夢中になって、練習しています。
ジャズテイストのフレーズを、ノンストップで弾き続ける。ただそれだけ。解説は特にないので、自分で分析する必要があります。
もう、めっさ楽しいです。タブ譜だと弾いている音がわかりにくいので、是非五線譜で。
内容↓
↓は「基礎」トレーニング編。
8分音符が4分音符になり、コードのリハーモナイズや基礎知識などが書かれているので、より親切です。即買いました(笑)。
ブルースの常套句
安東滋『ブルース・ギターの常套句』
ブルースこそ耳コピが当たり前のジャンルですが、楽譜で見ると気が付くことってたくさんあります。ブルースなら、コレ。
実は私、ブルースを弾くのは好きなのですが、ブルースを聴くのはあまり・・。ただ、個人的にGrant Greenとか好きで、サッチモの『St. Louis Blues』も大好き。ブルージーなジャズは別物・・怒られますね。「ブルースって聴く音楽じゃなくて、弾く(歌う)音楽じゃないの?元々はアフリカ系・・」もっと怒られそう。
踊るための音楽、暴れる(発散する)ための音楽、やばい薬・葉っぱを楽しむための音楽もある中で、決められたコード進行でもがく、魂の演奏。私の中でブルースは、演奏者が一番楽しめる音楽。
歌ものなら、ゴスペルが好きです。聖歌(賛美歌)とゴスペル、人種と宗教。エボニー&アイボリー、インディアン、ユダヤ、カトリック、イタリア系、アジア系、メキシコ系、アラブ系、イスラーム・・差別に満ちた移民の国、だからこそ?素晴らしい音楽が生まれた事実。彼らの言うソウルとは何なのか。
逸れましたが、本でブルースを学ぶのも悪くありません!
+α
「フレーズ系」の、動画を紹介します。
YouTubeで見かけ気になっていたのですが、遂に(誘惑に負け)登録。まだ全然見ていないので詳しいことは書けませんが、とにかく音がブルースです。
ブルース・チョーキングのくだりで「元々、初期のカントリー・ブルースはスライドギターで・・」の話から、さらっとチョーキングで(スライドバー無しで)スライドギターっぽいフレーズを弾いて「ぶ、ぶる~すや!」と感動して(支離滅裂)
私はブルースに詳しいわけではなく、特別好きなジャンルでも無いですし、「ブルースなんて好きに弾きゃあ良いんじゃねぇの」と思っています。
が、教わるなら(私の思う)「ブルースの音」を出せる人が良い。裏を返せば「ブルースギター・レッスン!」と謳いながらも、「ブルースっ”ぽい”だけの、何か(音選び・グルーヴが)ズレた」ギター講師ってYouTubeとかに結構いま・・やめよう。
ブルースの音を聴いて、練習するのが近道だと思います。
森孝人先生、しゃべるテンポはめちゃくちゃスローですが(笑)おすすめです。
【音感系】
メジャー・スケールを聴き分ける
フランツ ヴュルナー(著)『全訳コールユーブンゲン』
買ったというより、家にあった1冊。
コールユーブンゲン、音感トレーニングでは基本の1冊。
歴史の中で残った本は良い。リズムは無視して良いので、「五線譜を歌う→正しい音程を楽器でチェック」を繰り返してください。「歌メロコピー」なども混ぜつつ練習すれば、1周するまでもなく、「ドレミファソラシ」なら聴き分けられるようになるでしょう。
音源が必要な方は、別で用意してください。
耳で弾くギター
トモ藤田『耳と感性でギターが弾ける本』
トモ藤田さんはジャズの名門、バークリー大の先生。
『Just Funky』のコピーは、私のカッティング・プレイに大きな影響を与えました。
”ギターと音感”なら、この本がオススメ。難しいことは書かれていません。音大の先生らしく、正しい耳のトレーニング方法を、丁寧に説明されています。
以上です。この機会に本の整理もしたのですが、音楽系の本は絶版になるのが早いですね。良い本でも、中古でしか手に入らないものがいくつかありました。
出会った時が、買いどきなのかもしれません。
ありがとうございました。
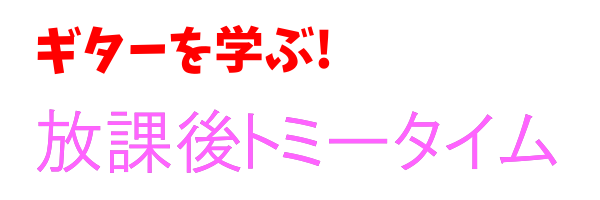




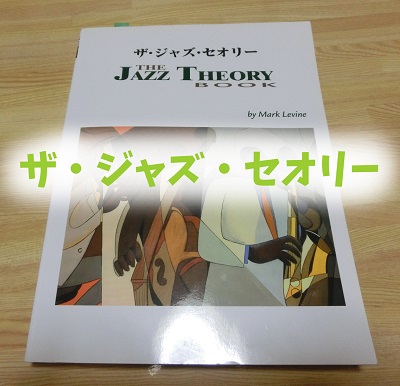









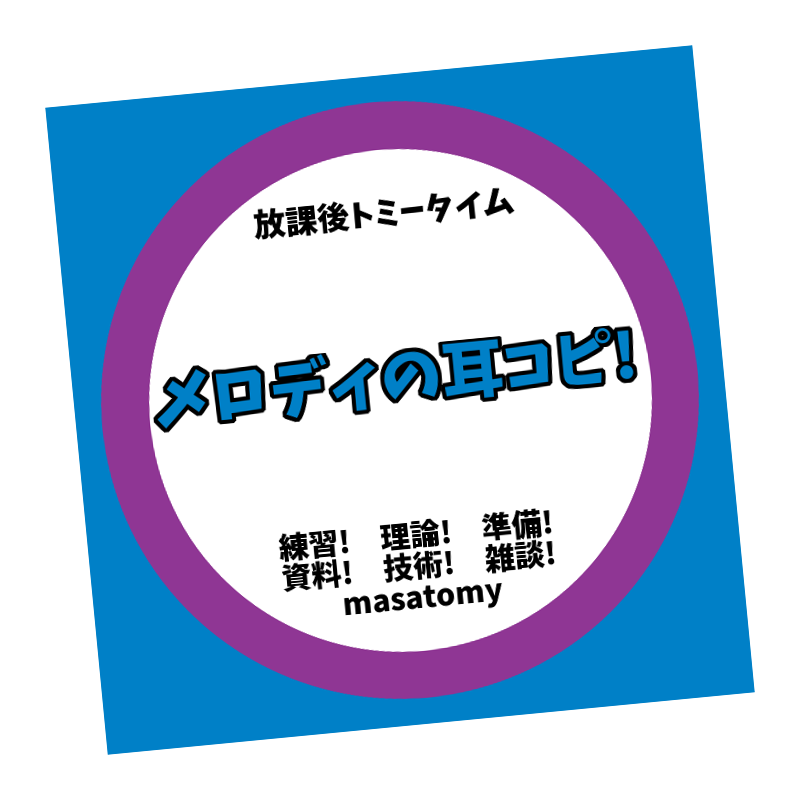

コメント