「耳コピってどうしたらいいの?コツは?」
「あんまり、得意じゃないんだよねぇ」
という方に是非おすすめしたい耳コピ練習法、それが「歌メロコピー」です。効果的な順番で、楽しく音感を鍛えましょう。

はじめに
テレビで流れているアイドルソング(難しすぎないキャッチーなメロディ)を聴いて、「ドレミファソラシ」でパッと歌うことができる
という方は、このページを読んでいただいても、得るものは少ないでしょう(それでも、読んで欲しいです!)。「単音なら余裕!」という方は「コードの耳コピ」も是非↓
このページでは、耳コピの練習法を紹介します。
今回やる内容はズバリ!歌メロディのコピーです。
「なんだなんだ?そんなの簡単じゃんよー」
という方には・・・少しレベルの高い練習方法も書きましたので、是非読んでいただきたい。
音楽において大切な要素である音感を楽しく、効率よく身に着けましょう。「楽しい!」は、成長速度に影響します。
耳コピ(音感)の真実!
はじめる前に、耳コピの真実といいますか、現実を確認します。
皆さんの周りにいる楽器歴1年以上の方に、この質問をしてみてください。
「〇〇さんの一番好きな曲って何ですか?ふーん、『◇◇◇』なんですね。へぇー、そんなステキな想い出があるんですかぁ。なんか私(僕)、その曲ド忘れしちゃったなぁ(白目)。その曲のメロディをドレミで歌ってみてくださいよ。ねぇ、ねえったらぁ!」
さて、どうなるでしょうか。
余裕で歌えるかもしれませんし、歌えないかもしれません。速弾きはできるのに、歌のメロディは歌えないかもしれません。そして、質問したことによって人間関係がギクシャクするかもしれません(※一切の責任は負いかねます)。
そうです。
「音感レベル」≠「音楽(楽器)に触れていた長さ」
なのです。
そして、「最近は特にこの傾向が強いのじゃ」と、年配者がおっしゃるのは世の常。
「模範解答(楽譜)が手軽に手に入るようになったから、耳コピをしなくなり、音感を育てる環境が失われた」みたいな現象かもしれません。ただ、実は(私の周りの)先輩方もそんなに音感があるとは・・こほんっ。
もちろん、楽譜自体は”悪”ではありません。楽譜でないと見えづらいことって結構あります。
では、はじめましょう。
耳コピ! 歌メロコピーで音感を鍛える
今回練習するのは、ただの耳コピではなく「歌メロコピー」です。
記事を書く前に「耳コピ コツ」で検索し、上から3、4記事ほど読んでみたのですが、「歌メロをコピーしましょう」と提案するサイトはありませんでした(※記事執筆時点では)。
「それ、既に耳コピできるヤツの方法や!」という内容が多く、どのサイトも読者に要求する音感レベルが高すぎるのではないかと震えました。
歌メロコピーのやり方は単純です。
①曲を再生して、Keyを探す。
②出だしの音を取る。
③曲を止める。耳コピ開始。
以上!
※Keyの探し方は↓で説明しています。
ポイントは、音程を意識すること。
「ドーラーと下がると、こう聴こえるのか!」
のように、「階名」と「耳で聴いた(脳内で再生した)音程」を、結び付ける作業を行ってほしいのです。
そして、その作業に便利なのが「ソルフェージュ」。
音程を階名(ドレミファ・・)で歌うことを階名唱法と言いますが、ここでは広い意味で捉え「ソルフェージュ」としておきます。詳細は2ページ目で説明します。
また、音感を鍛える前に、音程を理解しておかなければなりません。具体的には、「階名」と「移動ド」の知識が必要です。
階名は「ドレミファソラシ」で、音名が「ハニホヘトイロ」や「CDEFGAB」※ドレミはイタリア音名
移動ドは「ド(G) レ(A) ミ(B) ファ(C) ソ(D) ラ(E) シ(F#) in G」です。
詳しくは↓で説明しています。
以上を前提として、歌メロコピーを行います。
【ステップ0】耳コピのコツ
最初に、耳コピのちょっとしたコツを。
私の意見ですので、気に入らなければ無視してください。
(追記)「書いてあることが全然理解できない」というコメントをいただきましたが、本サイトを最初から読んでいただいている前提で重複する説明は省略していますので、ご理解ください。
要約すれば「耳コピ初心者の音感トレーニングには、歌メロコピーがベスト」ということです。音楽的な知識や用語も使用していますが、わからなければ飛ばしてください。
★歌詞ではなく、階名を思い浮かべる
歌詞ではなく、階名「ドレミファソラシ」を頭に浮かべながら耳コピしてみてください。最初のうちは、階名を歌いながらがいいでしょう。もちろん移動ドです。歌詞は本当に邪魔。
複雑なフレーズになってくると、階名より「2音間の音程(距離)」でとった方がわかりやすい場合もあります。(※階名「ミ→ファ→ファ#→ソ」ではなく、2音間の距離「ミ→半音上昇→半音上昇→半音上昇」と捉える方法。曲中でキーがコロコロ変わるor変わっているように聴こえるジャズなどは、こちらの方がわかりやすいのだとか)
例えば「半音で動くフレーズ」だと、楽器を始めたばかりの方でも、クロマチックの運指練習経験があれば「半音で動いてんなー」と気が付くと思います。アルペジオフレーズの演奏経験があれば「お、なんや3度のカタマリ弾いとんなぁ」と感じるはず。それをレベルアップさせていきます。
が、歌メロに関してはドレミがわかりやすいです。
★短いフレーズで区切って、音程を覚える
英単語を覚えるのと同じで、例えば「ドーラー」と下がるフレーズが出てきたら、それをパーツとして、フレーズごと音程の響きを覚えてしまいます。次に「ドーラー」が出てきたときには、一発で当てられるように。
長いフレーズで覚えても、応用が利きにくいです。また最初のうちは、「ド」が絡むフレーズから優先して覚えてみてください。
★正しいフレーズを復唱する
最初のうちは、頭に思い浮かんだ階名と、実際の階名は一致しません。ですので、楽器で正解を確かめてから復唱する方法がおすすめです。
一度間違える→悔しい、この野郎!→正しい階名を確認→再び歌って脳に焼き付ける
という手順で、脳科学的にもスムーズに成長できる・・はず。「間違える」→「悔しい」→「なんだ正解はこれかぁ!」→「脳の神経回路ピピピ!」というイメージ。
★マイナーキーは主音「ド」で
主音ラ、つまり「ラシドレミファソ」でマイナーキーを考える方法はおすすめしません。
理由は単純で、「ラに着地するのは、気持ち悪い」と(私が)感じるからです。相対音感を鍛えるためには、おそらく主音ドで統一した方が効果的。「ラに着地する」という無駄な音程感覚を身に付けなくてすみます。※私個人の意見です
マイナーキーは主音ドで、「ドレミ♭ファソラ♭シ♭」。自然的短音階(ナチュラルマイナースケール)の「ミ♭、ラ♭、シ♭」と長音階の音程がつかめれば、残りは「レ♭、ファ#(ソ♭)」だけです。この2音は目立ちますし、特にドと同時に鳴らした音程が特徴的なので覚えやすい。マスターすれば12音を網羅できます。
★目をつむる
これが意外と効果的。
私の場合、目をつむって音を聴くと、1.5倍は音に集中できます。いや、正確には目を開けたまま耳コピしてますが、考え事をしてるときのように、目からの情報は遮断してます。
耳コピに慣れていない方は、普段音楽を聴くときよりも、数倍は音に集中してください。今回は歌のメロディに集中。英語のリスニングテスト以上に集中。できることなら、目でも音を見たいくらい。
☆音感チェック
それでは、少しだけ音感をチェックしてみましょう。
Key=Cです。
余裕だと思います。
なんでこんなもの作ったのか私もわかりませんが(笑)、いや、無料ソフト使ってみたくて作りました。クリック音(メトロノーム)を入れたかったのですが、やり方がわからず。
次は少し、レベルアップ。Key=Eです。
主音ドをEに移動させて、Eメジャースケールは「E(ド) F#(レ) G#(ミ) A(ファ) B(ソ) C#(ラ) D#(シ)」となります。
いかがでしょう?
動画を作っているときには気がつかなかったのですが、前後のつながり、伴奏なしでいきなりメロディが出てくると・・少し掴みづらいですね(おい)。
例えば「ミレドー」や「ラシドー」など「〇→ドー」のパターンは、数時間で理解できるようになります。
☆逆方向に戻る
おすすめはしませんが、フレーズの最後に無理やり(主音確認のため)ドをねじ込んで「フレーズを”逆方向”に戻る」みたいな遊びもしていました。
「ミファミファソー」なら
「ミファミファソード」とねじ込んで
「ドソファミファミー」と逆方向に戻る
※効果があるかは不明
ただ、音程は強く意識できます。
紙か何かに書いて1曲まるまるやってみると、「文字(音符)→音」の脳内変換能力が上がるような気がします。”逆方向”なので違和感のあるフレーズも出てきますが、「まぐれ正解」を排除するので、逆に練習になります。
☆楽譜を脳内再生
歌のメロディは「ミレドー」「ミファソー」など、音階(スケール)をなめらかに上下するフレーズが多いので、音感トレーニング入門にピッタリです。
そのうち、シンプルな歌メロは、聴いただけで自然と階名が頭に浮かぶようになります。逆に、階名を見ただけで音が頭の中で鳴るようにもなるでしょう。
たとえば「ドレミーレド ドレミレドレー」(チャルメラ)
文字だけなのに、メロディが頭に浮かびませんか?
このレベルが、上がっていきます。譜面から音が聴こえ、楽器なしでも(単音なら)脳内演奏ができるように。大袈裟でも何でもなく「ドレミファソラシ」だけの歌メロなら、すぐ脳内演奏できるようになるでしょう。
適当な楽譜で練習すると捗りますが、私のおすすめは「コールユーブンゲン」です。リズムとかそんなものは無視して(しなくてもいいです)、呪文のように歌ってみてください。だんだんイライラして、テンポが上がってきます(笑)。※正しい音はキーボードか何かで確認してください。
☆歌えるくらい覚える?
歌メロの耳コピができない状態で楽器フレーズをコピーするのは、少し無理があります。
「耳コピ コツ」で検索ヒットする記事の主な方法は「フレーズを歌えるくらい覚えてから、耳コピをしましょう」というものでした(記事執筆時点では)。
しかし、この方法はそもそも「歌えるフレーズを、ドレミに変換できる(何らかの文字や記号に変換できる)」というのが前提です。
フレーズを歌えるくらい覚えた→脳内で文字(記号)に変換→楽器で弾く
ということであって、間の「変換」をすっ飛ばして、単に楽器の音当てゲームになるとキツい。ただ脳内レコーダーの音と照合しているだけです。
もっと言うと、歌えるくらい覚えなくても音程はコピーできます。
言語で考えるなら「私はギターが弾けます(日本語)」と「Я могу играть на гитаре(ロシア語※Google翻訳活用)」くらい違う。日本語だと意味がわかるので1度聴いただけで復唱(コピー)できますが、ロシア語だと意味がわからない人にとっては、音だけで(復唱できるまで)覚えないといけないのでベリーハードです。※ネイティブの発音(演奏のニュアンス)は実際に発音(演奏)して真似ます。
もちろん「フレーズを2秒単位で止めて、弾いて、間違えて、合う音みっけ。また次の2秒・・」と繰り返す方法もあります。
でも、どうせ音楽を楽しむのなら、音感も鍛えたい。
☆1音進むごとに音階を確認する
(追記)「本当に音感が無い人は(中略)何が間違ってるのかがわからない」という貴重なコメントいただきまして、私なりに練習法考えてみました。
歌メロ1音進むごとに「ドレミファソラシ」を確認するという方法はいかがでしょうか。
例えば「①ド②ミ③ファ④ソー」という歌メロなら
①(A)1音目を歌う(歌詞ではなく”アー”など)
→(B)ドレミファソラシをキーボード等で弾いて確認(※もちろん移動ドで)
※”アー”と声を出し続けたままキーボードで確認すると、正解の音が見つけやすいです。
→(C)正しい音程(ド)を見つけたら、階名で度歌う
→(D)正しい音程にたどり着くまで、ドから順に歌っていく
②(A)2音目を”アー”で歌う
→(B)キーボードでドレミファソラシを確認
→(C)正しい音程(ミ)を見つけたら階名で歌う
→(D)正しい音程がミなので、ドから順にド→レ→ミと歌って(キーボードに合わせて)、だめおしで正しい音程(ミ)を歌う
③(A)3音目→(B)→(C)ファを歌う→(D)ドレミファ、ファーと歌う
④(A)4音目→(B)→(C)ソを歌う→(D)ドレミファソ、ソーと歌う
のように。
音は振動なので、歌と楽器を同時に鳴らして確認してみてください。キーボードと歌の音程が重なると1つの音のようにも聴こえますが、ずれているとハッキリ複数の音に聴こえます。
何度も何度もドレミファソラシを確認することで、頭の中に音程が記憶され、正しい音程を探しやすくなるのかなとイメージしているのですが・・いかがでしょう。
ちなみに「ドミファソー」はテレビアニメ「けいおん!!」の劇中歌『天使にふれたよ』Aメロの1フレーズ。そして『聖者の行進』の出だしのメロディです。他の曲だと・・
私は「脳内で記憶している音程(基準音からの距離感)と結びつける能力が相対音感」じゃないのかなと思っていますが、「本当に音感が無い」と感じていらっしゃる方には、何かもっと違う効果的な(”音痴の治し方”のような)アプローチがあるのかもしれません。単に鈍い(人以上に練習すれば伸びる)ということではなく、共感覚のように、音の捉え方が他の人と違うなど根本的理由・・あるのでしょうか。
【ステップ1】覚えている曲で練習
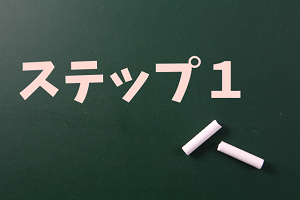
【ステップ1】は「正しい音程を脳に焼き付ける」練習です。
メロディを完璧に歌える曲を使います。歌詞は不要。
手順は
①曲を再生して、Keyを探す。
②出だしの音を取る。
③曲を止める。耳コピ開始。
当たり前なので省略しましたが「①Keyを探す」には「そのキーのスケールを頭にインプットする」も含まれます。
例えば①で「KeyGのメジャースケール」と判別できたら、「G(ド), A(レ), B(ミ), C(ファ), D(ソ), E(ラ), F#(シ)」を楽器で弾いて(できれば一緒に歌って)脳にインプットします。そして、そのインプットした正しい音程を基準に、耳コピしていきます。
ポイントは③です。
必ず曲を止めた状態で、耳コピ(ギターなどで演奏)してください。
探り探りで構いません。というより、最初は当然そうなります。途中で間違えたらまた同じ曲を練習し、3周くらいやると覚えてしまうでしょう。
曲をクリアしたら次は、
「”ドーラー”と下がると、こんな響きなのか」
というように、パーツごとに分けて音程を覚えてみてください。
歌詞がどうしても浮かんでしまう場合は「るるるー」や「ふふふー」と1フレーズ歌い、その音を耳コピするといいかもしれません。
また最初の内は「途中で一旦ドに戻る」のもおすすめです。「ソラソー」というフレーズなら、「ソラソー ファミレドー」のように一度ドまで下がり(又は上がり)ます。ドからの距離を繰り返し確認するだけでも、習得スピードが上がります。
慣れてきたら、ド以外の好きな音にも飛んでみてください。脳内でイメージした音と、実際に弾いた音が一致すれば、アドリブも楽しくなります。
※微妙な音(ミとミ♭の間など)は、各々で解釈を。そもそもチューニングが違う場合は、A=440Hzから前後に調整してください。生楽器、ちょい古めの曲は低めのチューニングが多い印象。
※次ページ「#や♭の歌い方(階名唱法)」
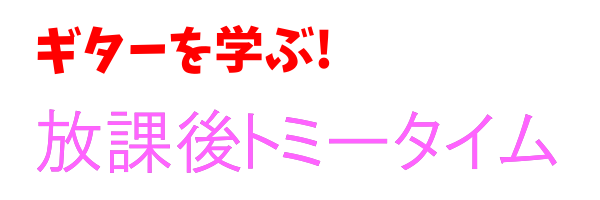
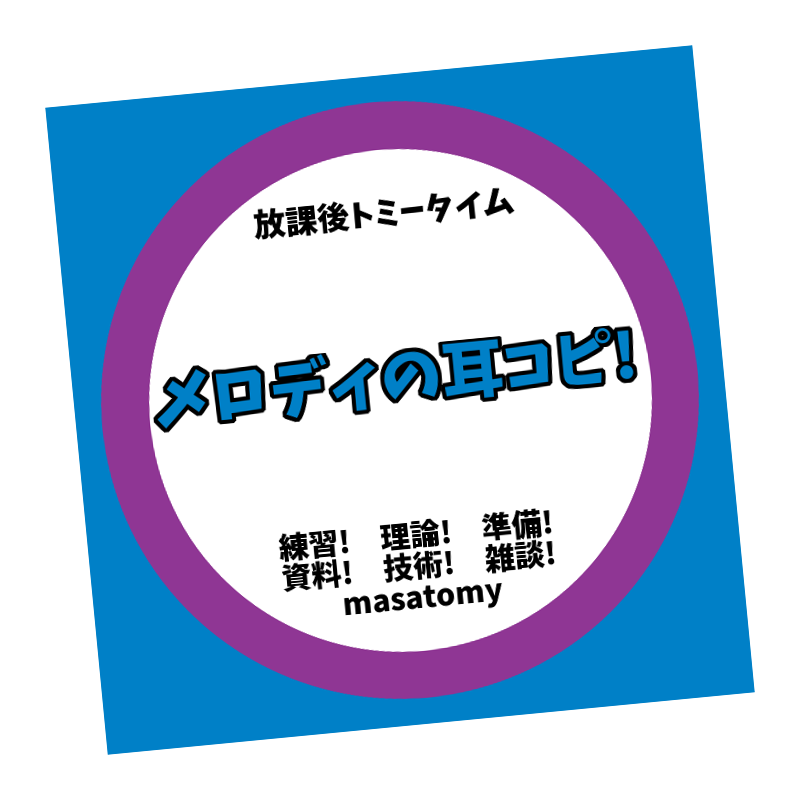
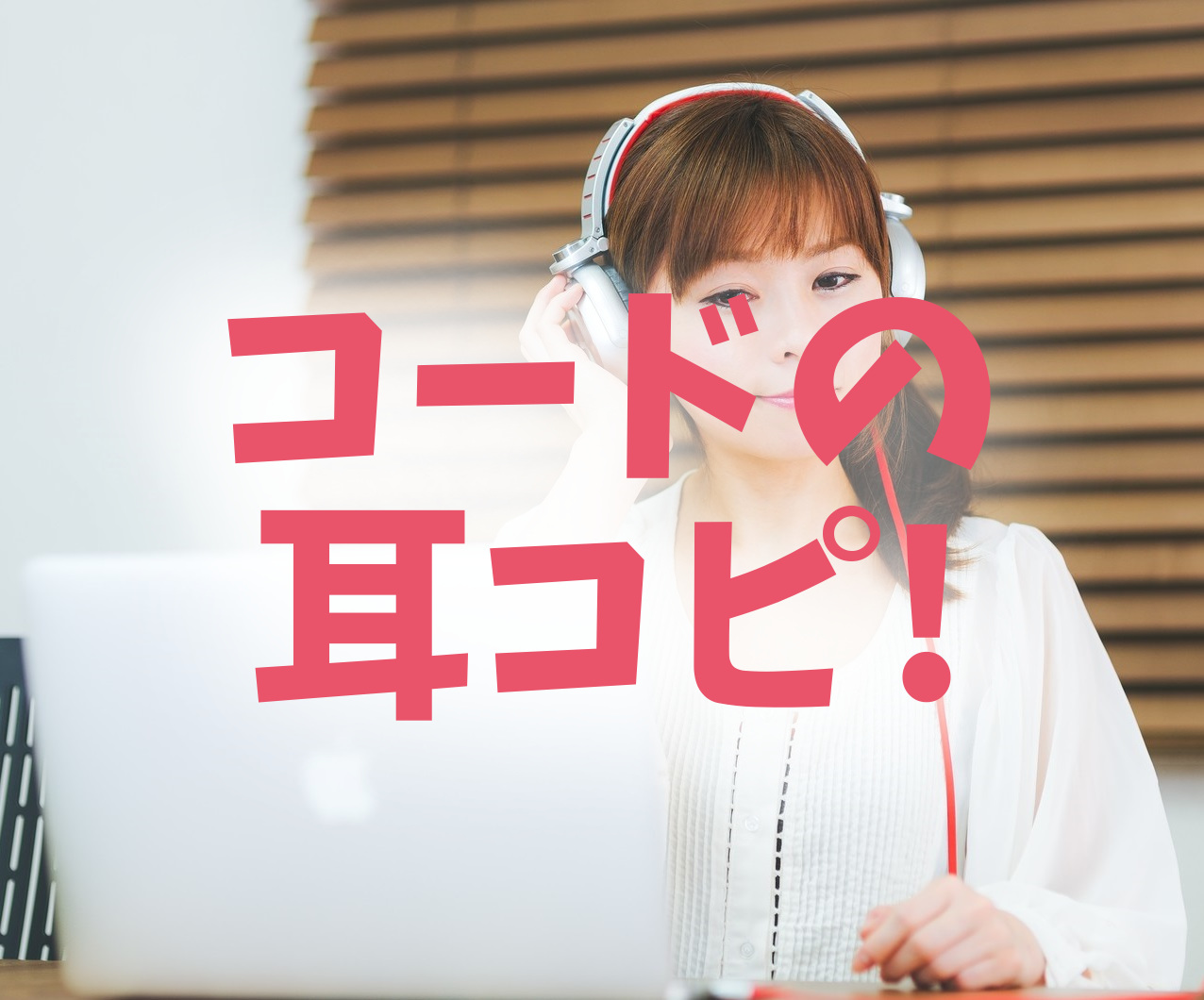

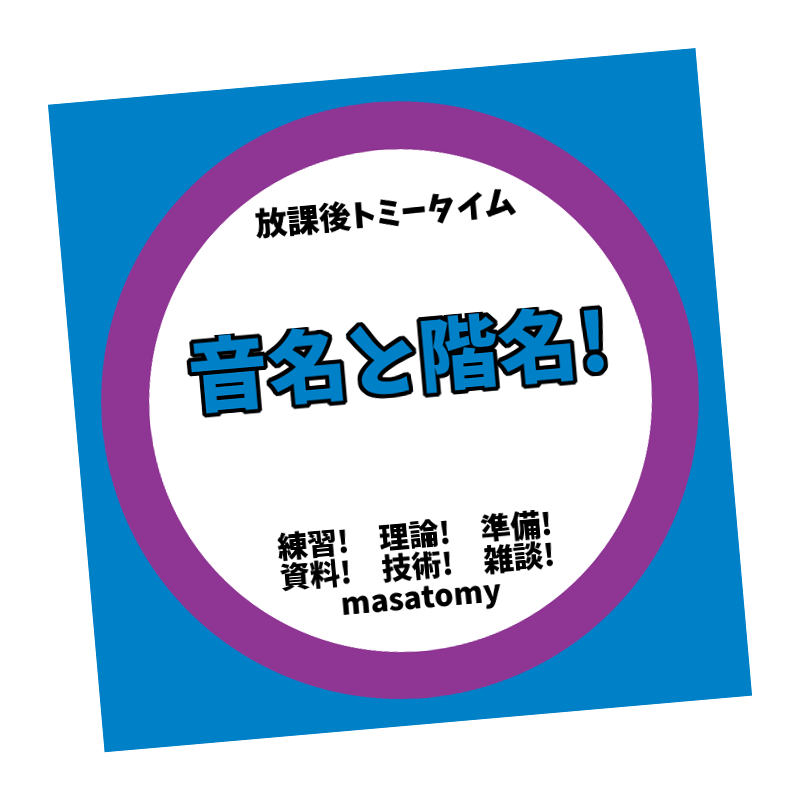
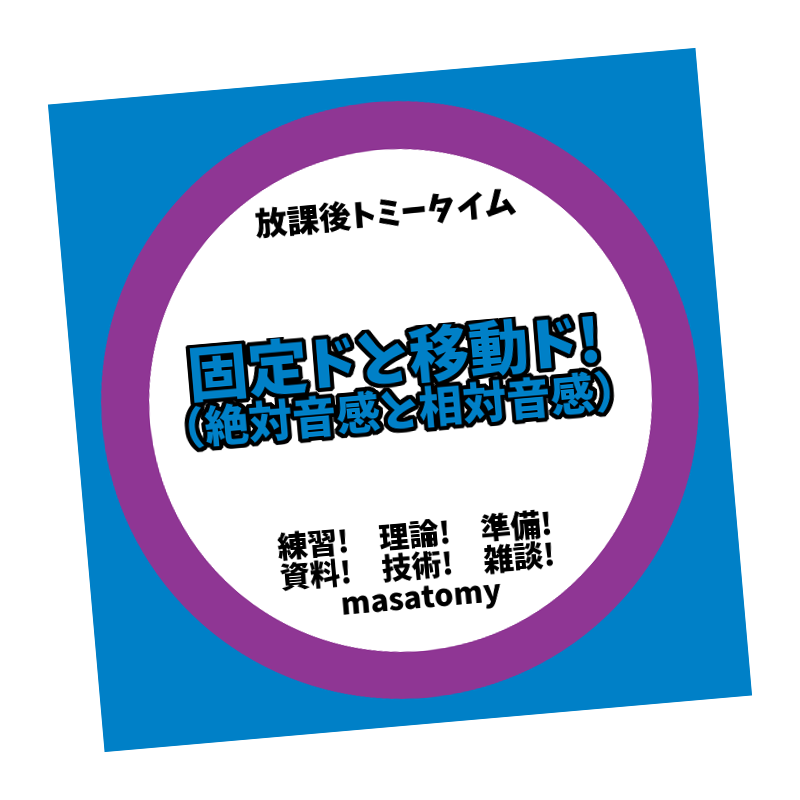
コメント
キーボードの出してる音と、自分の出してる音が、同じかどうか分からないぐらい音感ない状態でしたが、何回もやっているうちに、Keyが特定できるようになってきました。まだ確信をもって「keyはこれだ!!」とは言えないし、間違いも多いですけど、分かるようになったのはこのサイトの記事のおかげです。ありがとうございます。耳コピできるまで頑張ります。
コメントありがとうございます!
最近、素晴らしい音感トレーニング動画見つけましたので是非!
音楽学校に通われたプロの方のレッスン動画です。
いきいき音楽科さん(↓のURLコピー&ペーストで飛べます)
youtube.com/watch?v=1RK369_PJWE
君が代はどう歌うのがいいか教えてください。
1をドに固定するということは、DドリアンなのでDをドとして歌うのがいいですか?
基準とする音源がわからないのでキーは何とも言えませんが、今歌ってみた感じだと「きみがーよーは」は「レドレミソミレー」がしっくりきます。私が最初の2小節で終止感を感じたのは「きみがー」の「み」の音程です。
何かしらの(民族的な)旋法を使っている印象も受けますし、特に後半は終止感が薄いメロディで(ラ・マルセイエーズのように大袈裟に感情を煽ることもなく、神秘的かつ不気味で、歌い終わった直後ジブリ映画の神々が現れそうな畏れを感じさせる余韻にも繋がる、この曲の魅力だと感じますが)、何より伴奏が無いので難しいですが、(私は)ドリアンでは無いと思います。
どせいさんが、ドリアンだと感じた箇所を教えてください。
ちなみに、「1(スケールの主音)=ド」に設定するのは”相対音感的に理解しやすくする”のが目的であって、何でもかんでも「1=ドにすれば良い」ということではありません。旋法が変化してもドはそのままのときもありますし、その逆(転調に合わせてドも変化させる場合)もあります。「どのように歌えば”自分が”音程を理解しやすいか」で決めてください。
本当に音感が無い人は何度聞いても、わからないんですよね(私のことですが)
階名と聞いた音が合ってるのか合ってないのかすらが分からない
もしかしたら偶然で合うかもしれませんが次のフレーズも偶然で見つけるしかありません
そもそも間違っていたとしても何が間違ってるのか(一音違うのか二音違うのか)がわからない
>>書いてあることが全然理解できない上にステップ0もできやしない…
というのはそういうことなのです、僭越ながら代弁させていただきました
助けて下さい
>>書いてあることが全然理解できない上にステップ0もできやしない…
というのはそういうことなのです
「言いたいことはわかるけど全然できない(効果が実感できない)」ということでしょうか。「書いてあることの意味がわからない」ということでは無いでしょうか?いずれにせよ言葉足らずで、コメントお返ししづらいです。
また「全然理解できない」とだけ書かれる方は、”理解したい(成長したい)”という意欲が薄いなと感じます。「ここが理解できない」と書かれた方が、コメントされた方にとって建設的であろうと感じるのですが。理解できなかったことへの憂さ晴らしコメントであれば、やめて欲しいです。
脱線しました。
ショウユさんのコメントに戻り、本サイトは楽器趣味系のサイトですので「カラオケで音程を外したら気が付く」くらいの方を意識して書いています。私自身、その筋(音楽教育?)の専門家ではありませんので「本当に音感が無い」と感じていらっしゃるショウユさんに適切なアドバイスはできません。申し訳ありません。
「音感が無い」ということですが、例えばキーボードでドを鳴らしながら、その音に合わせてドの音を発声することはできますでしょうか?また「音が合ってるのかわからない」ということですが、キーボードと声で同時にドを出した場合、同じ音だと認識できますでしょうか?
音は振動ですので、同時に鳴らしてみると「合ってるorあってない」がわかりやすいです(合ってる場合、重なって1つの音のようにも聴こえますが、ずれているとハッキリ複数の音に聴こえます)。2つ同時に鳴らして「ずれているorずれていない」を認識できないようでしたら、本当に音感は無いのだと思います。
(どの音程かわからなくても)2つの音が「ずれているorずれていない」が理解できるようでしたら、少なくとも音感はあります。あとは自分のレベルに合ったトレーニングです。
階名に関しては、歌メロ1音進むごとに「ドレミファソラシ」を歌ってみるとコツがつかめるかもしれません。記事に追記しますのでそちらをご覧ください。
書いてあることが全然理解できない上にステップ0もできやしない…
ごめんなさい。
どこが理解できないか具体的に書いていただけないと、こちらもコメントできやしない…
ステップ0は耳コピのコツです。”できない”の意味するところは何でしょうか。
記事で伝えたかったのは「歌メロディの耳コピからはじめましょう」ということです。ただ、それだけだとあまりに不親切で記事として成り立たないので、コツや少し専門的な説明を足しました。
本サイトを最初から読んでいただいている前提で書いていますので、「移動ド」や「主音ド」など音楽の基礎が理解できていないという意味であれば、ページ内のリンクから該当の記事をご覧ください。「耳コピ初心者」の方に向けての記事です。「音楽初心者」の方が馴染みの無い用語は別で説明しています。
また「簡単にできる」ことを意識して書いていません。
「ドレミの3音からはじめる」でも良いでしょうが、すぐ飽きますし、実践的ではありません。「歌のメロディを耳コピする」のが練習の順序として適当だと私は考えました。
難しければ「鍵盤のドを鳴らし、合わせてドを歌ってみる」など音楽教室でありそうな、初歩の練習からはじめてみてください。
音階7音ではなくて半音があるから12音あるんですよね 当然半音もミミコピということでしょう 記述が12音ないので、、
音階は基本的に7音です。
12音から7音を選び並べた、音階です。
メジャースケールなら「ドレミファソラシ」
ナチュラルマイナーなら「ドレミ♭ファソラ♭シ♭」
ペンタトニックスケールなら5音ですね。
12音を音階として捉えるならクロマチックスケールですが、12音のスケール感を身に付けるのは難易度高すぎです。メジャースケールにミ♭を足して8音にするだけでも難易度が上がるでしょう。今回のテーマは「歌メロで音感を鍛える」なので「メジャーやマイナースケールの音感をまず身に付け、その過程で残りの音程感覚も身に付け、最終的に12音全ての音感ついたら嬉しい」という感じです。